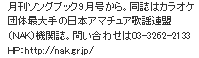殻を打ち破れ235回
「そうか、来年でもう60回か。俺、日比谷野音の第1回から見てる。感慨深いなぁ」
「その第1回に出演した方、もう誰も居ません。主宰者の石井好子さんをはじめ、皆さん亡くなってしまって…」
7月14日夕、渋谷・オーチャードホールで開かれた「パリ祭」の開演前、窪田豊プロデューサーと僕の立ち話だ。年に一度のシャンソンの祭典。2日続きのイベントで、珍しくシャンソンを歌う藤あや子が13日、ボサノバの小野リサが14日のゲスト。鳳蘭、菅原洋一、前田美波里、美川憲一、山本リンダ、クミコあたりが日替わり出演、30人近くの歌手たちがノドを競うが、このジャンルはベテランが多い。構成演出の髙平哲郎の今回の趣向は、第一部が「偉大なる三大B」と名付けて、頭文字がBのジルベール・ベコー、バルバラ、ジャック・ブレルの世界、第二部はエンリコ・マシアス特集。
演歌全盛期育ちの僕が、シャンソン界に首を突っ込んだのは、石井好子の知遇を得てのこと。彼女の事務所と僕の勤め先のスポーツニッポン新聞社が日本シャンソンコンクールを共催、加藤登紀子をはじめ若い才能を多勢送り出した。お陰で高英男、深緑夏代、芦野宏、岸洋子らとの親交にも恵まれた。
しかし、石井音楽事務所のスタッフからは、危険分子呼ばわりを受ける。若い歌手たちがフランスの“本家”の歌に、「型」から入ることばかりに腐心する姿勢を批判したため。ピアフ風とかアズナブール風とかを競うより、作品のココロと自分のココロを考え合わせなきゃ、演歌・歌謡曲をご覧よ、それがちゃんと出来てるよ!
≪しかしパリ祭もいつのころからか、ひどく健全な大音声大会になったものだ…≫
今回の客席で僕はそんな感想を持つ。経歴を見れば多くの歌手たちが、大学の声楽科出身の本格派である。訓練された美声を快く響かせて、それはそれでひとつの魅力だろう。しかし、昔から「人生の機微を歌う文学性」を語った鬱屈や人肌の説得力が後退してはいないか?
ほほう…と、彼女らなりの色あいにじませて感じたのは『神の思いのままに』のやまこし藍子、『リヨン駅』のリリ・レイ、『ミモザの島』の花木さち子あたりで、大音声タイプの完成型と思えた『アムステルダム』の伊東はじめは、この道55年のキャリアだった。
それから4日後の同じオーチャードホールで、僕は「時には昔の話を・加藤登紀子コンサート2021」を聞いた。
「どんなに暗い時代にも、人は輝いて生きようとします。信じられないほど罪深く愚かだけれど、きっと本当は素晴らしく生きられるはずだと、信じて」
加藤はプログラムにそんなことを書く。コロナをめぐるその場しのぎの政策への不信、先行きが見えない焦燥感の中で、強行された東京オリンピックと見事なほどのメダル・ラッシュ。それはそれこれはこれ…と、相反する思いを別々に抱えながら、失速する日々…。
「でもね、長く遠い未来としても、その第一歩が“今日”だと考えたいのよね」
ふつうコンサートは歌の合い間にトークが入る、いわば“つなぎ”の役割。加藤の場合は逆で、語るべき思いが先にあって、合い間にそれに似合いの歌がはさまる。そんな人間味とエッセイを聴くような手応えが、彼女のファンをとりこにするのだろう。
『ひとり寝の子守唄』も『カチューシャの唄』も『愛の讃歌』もアンコールの『百万本のバラ』も、彼女が「混惑」の時代と決意を語る舞台で、ちゃんと役割を持っていた。
≪非常事態宣言の乱れ打ちと東京五輪なぁ≫
アクセルとブレーキを踏み間違えたのは、高齢ドライバーだけじゃないよな!