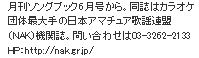殻を打ち破れ 第103回
荒木とよひさの仕事を「当代切っての女心ソングの書き手」と評したことがある。
「それじゃ、俺はどうなるのよ!」
酔余、吉岡治が口をとがらせたのには閉口した。『さざんかの宿』『細雪』『天城越え』と、女心を描破した実績に応分の自負があるのだろう。
「誰が一番とは言ってない。あんたが確立したのは“艶歌”で、ごく日本的な情念の世界さ。荒木が書くのはその後というかその次というか。女のすみかがマンションに変わったよな」
酔いに任せて、僕も言いつのった。「ふ~ん」と吉岡は、不承不承の顔をした。
それをさかのぼる10何年か前、吉岡と僕は赤坂で偶然出会った。宇崎竜童がやっていたブギウギハウスという店で、この夜も二人は酔っていた。
1970年代、シンガーソングライターの台頭が目ざましかった。フォークソングを中心に、彼らは率直に時代と自分を歌い、僕らの問答はその意味やパワーについて、往きつ戻りつした。
ラジオの時代、吉岡は放送劇の作家だった。のちに三木鶏郎に誘われて彼の冗談工房に入る。風刺ソングを量産したグループである。そんな中で身につけた時代感覚と、大衆歌謡の中身がかけ離れて思えてか、彼は歌謡界に自分の居場所を見つけきれずにいた。
「転職も考えてる。大阪のダンボール会社でどうかと言ってくれる人もいて…」
弱気の彼に驚いて、僕はやむを得ず語気を強めた。
「はやり歌は売れてなんぼの商売でしょう。その歌ひとつに何を託すか、どこまで託し切れるかは、歌書き本人の粘着力次第でしょうが…」
したり顔に突き放して、何とも薄情な対応ではあったろう。
やがて吉岡は、日夜うた論議を尽くす同志、中村一好ディレクターを得る。彼は東大安田講堂組の議論好きで、二人の意見は「大衆音楽の娯楽性」で一致する。『真っ赤な太陽』『真夜中のギター』のあとの吉岡の長いブランクは8年余。眼からウロコが落ちた第一作は都はるみの『大阪しぐれ』で、以後はイッキ・イッキ!のヒット曲量産。演歌書き一方の旗頭にのし上がった。
「おやじがその筋の人の女に手を出して、東京をところ払になってさ。俺はおやじと炭坑を転々とした。北の果て樺太まで二人連れの旅さ…」
問わず語りに語った、彼の少年時代である。樺太は今のサハリン。とすると吉岡がそこに居たのは終戦前で小学校低学年か。そんな生い立ちが影を落としたかどうか、吉岡は生きること、愛することを悲哀の側から突き詰めた。「後ろ向きの美学」を自称したゆえんである。
5月17日、心筋梗塞で死去。76才。5月24、25日が通夜葬儀で場所は築地本願寺。贈られた花300基、弔問した人900人。葬儀委員長を務めた僕は、この時「当代随一の艶歌書き」と3つ年上の親友を同時に失った。