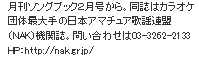殻を打ち破れ 第110回
北海道・鹿部町は人口5000人ほどの漁師町。函館空港から川汲峠を越え、噴火湾沿いに北上、車で小一時間のところにある。元気なころの星野哲郎は、毎夏ここに通って“海の詩人”のおさらいをした。払暁、沖に出て定置網をひき、朝食は番屋で獲れたての海の幸がおかず。昼前から漁師たちとゴルフに興じ、夜は夜とて談論風発の酒…。
ここ20年近くのお供は、作曲家岡千秋と作詞家里村龍一が助さん格さん。それに僕が加わって、夢みたいな日々を過ごした。受け入れ側のボスは地元の有力者、道場水産の道場登社長とその一統。“たらこのおやじ”の異名を持つ道場氏は、自称星野哲郎北海道後援会の会長。歌好きゴルフ好き酒好きで、いつも少年みたいな眼を輝かせる。
鹿部にバクの会というのがある。青年商工会議所漁港版ふう。星野は函館空港でそのメンバーから声をかけられた。「暇な時に遊びに来てよ」―著名人にはよくあるケース。生返事ですり抜けたら後日、「いつ来るのよ。あれは場当たりのお愛想なの?」と、追い討ちがかかった。北の町の人の率直。胸を打たれた詩人の即応。以後30年近い親交が生まれた。
新宿の、なじみのホステスさんたちは酔えば彼を「テツローッ!」と呼び捨て。道ばたで餅を焼くおにいさんは「横井弘先生たちはあの店に…」と、歌書き仲間の動静を耳うちする。共同トイレの扉の不具合を訴える彼に、屋台のおかみが「押してもだめなら引いてみなよ!」と怒鳴って、ヒット曲のヒントを提供した。星野はいつも巷を彼の書斎にした。
人づきあいの視線が、わけへだてなく平らなのだ。終戦直後、東シナ海を漁場とする船に乗る。外国航路への夢を大病で断念、作詞家に転じた経緯はよく知られている。星野は青年期に、はるかな水平線に注いでいた視線を、そのまま市井の人々の営みに移したのだろう。挫折感の深さが、弱者への励ましやいたわりを生む。彼が書いた歌は全部、人生の応援歌になった。
故郷・山口県周防大島を軸に、「全日本えん歌蚤の市」を主宰した。応分の力量を持ちながら、陽の目を見ない歌手たちに脚光を!がコンセプト。その熱い思いに賛同して、作詞家の石本美由起、作曲家の船村徹ら、大勢の歌書きたちが参加した。あれは彼が、生涯の仕事場とした“演歌界への返礼”であり、ふるさとの“町おこし”の企てでもあったろう。
僕は昭和38年に星野と初めて会った。スポニチの内勤あがりの記者28才と、働き盛りの詩人39才だった。以後正確には47年、望外の知遇を得た。記者の仕事も芸事と同じで、「教わるよりも盗め」が基本。盗み放題を許されて触れて彼の詩業とひととなりは、僕の宝の山になり、ついに彼が心の師になった。
2010年11月15日、僕らは“情の詩人”星野哲郎を見送った。今年2月には周防大島、夏に北海道・鹿部で、星野の会が開かれる。みんなはきっと、大いに飲み、大いに語り、大いに星野作品を歌うことになるだろう。それがよくある偲ぶ会にならないのは、僕らにとって星野は、決して「居なくなることなどない存在」だからだろう。