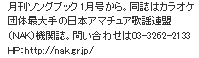殻を打ち破れ121回
「結局は、ヒット曲があってこその歌い手だと思うの。楽屋の席順だって、それで決まるんだし…」
久しぶり会った北原ミレイがポツンとそんな事を言った。屈託のない世間話にはさまった、妙に生々しい本音…。 ≪えっ? 楽屋の席順?≫
僕はその一言にひっかかる。歌手生活も40年を越え“歌巧者”の評価も定まり、とうに一家を成したこの人が、まだそんなこだわりを、あえて口にするのか?
デビュー曲『ざんげの値打ちもない』がヒットしたのは、1970年。この1曲で僕は作詞家阿久悠と歌手北原ミレイを同時に発見、ものの見事に舞い上がった。この作品が流行歌の流れを変える! 変革の70年代、阿久は新時代の旗手になる! それを象徴するのがミレイだ!
当時新聞記者だった僕は、そう書きまくり吹聴しまくった。14才で愛に飢え、15才で男に抱かれ、19才で男を刺そうと待つ女…。ナイフの青白い光が眼を射る映像的感覚、ドス黒いストーリー性、早熟の時代を言い当てた視点、流行歌のタブーへの挑戦などが、衝撃的で新鮮で、文学的ですらあった。はばかりながら後に阿久は、
「そう言うふうに評価してくれる人がいるなら、本気で作詞をしてみようと思った」
と自著に書き、
「小西さんが居なかったら、あの歌はきっと世に出なかった」
と、ミレイは今でも述懐する。しかし――。
彼女はそれから4年後に歌うことをやめている。『ざんげ…』が作った“暗いイメージ”に耐えられなかった。彼女の歌手としての夢と、あの世界の現実には、ギャップが大き過ぎた。ミレイはあの主人公を演じ続けることに疲れ果てた。止めを刺したのは阿久が書いた2作めと3作めで、タイトルは『棄てるものがあるうちはいい』『何も死ぬことはないだろうに』――。
ミレイが歌いたかったのは、例えばペドロ&カプリシャスの『別れの朝』など、ロマンチックでおとなの気分のポップスだった。ところが彼女は『石狩挽歌』(75年)『漁歌』(83年)とまた“暗め”の回り道をして、やっと辿り着いたのがここ10年ほどの『女友達』『雨の思い出』『ショパンの雨音』…。それまでの試行錯誤の中で、ミレイは一体、どのくらいの辛い、口惜しい思いを背負い込んで来たのだろう?
転機を作ったのはカラオケである。歌う現場で直面したのは「歌ってもらってナンボ」の実態。売れないままのいい歌なんてない。売れて歌って貰ってはじめて、いい作品になるという現実。それと長年の夢を突き合わせたのが、和製シャンソンとも言うべき作品群だった。今、その集大成みたいに彼女は、新曲『ためらい』を歌う。ちあき哲也の詞、ひうら一帆の曲が、確かになかなかの仕上がり。
さて新年…と、僕は考える。この路線とこの作品でミレイは今楽屋でどんな席順を得ているのだろう? この先ずっと彼女は、どんな席順を確保して行くのだろう?