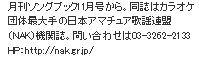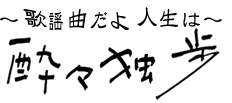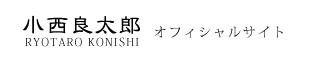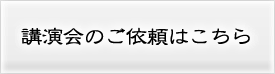殻を打ち破れ143回
演歌の"決め手"は歌いだしの歌詞の2行分、そこですべてが決まる! この原則は大ベテランの藤田まさと、師匠の星野哲郎、親交のあった吉岡治らの仕事から、骨身にしみるほど学んだ。「歌詞」を「歌の文句」と呼んだ昔々から、大勢の詩人たちもそこに知恵をしぼった。いい文句には必ず、いいメロディーがついて来る。それを目安にここのところの新曲を聴いていたら――、
♪涙買いましょう 外は凍(しば)れる 人の涙が 雪になる...
というのに出っくわした。大石まどかが歌う『居酒屋「津軽」』という作品。何?涙を売り買いするのか?と意表を衝かれて聴き進んだら、酒場の女将が客から、笑顔で受け取る酒代をそう表現していると判った。作詞者は内藤綾子、この人のこだわり方はなかなかなもので、二番の頭が、
♪愚痴も買いましょう 吹雪止むまで 荒れた心じゃ 明日がない...
と、時化を嘆く女房を持つ相手を思いやり、三番では
♪釣銭は出しません 全部貰わにゃ あんた 涙を 持ち帰る...
とまで言い切るのだ。どうやら「津軽」という名の居酒屋は涙の吹きだまり。心が折れた荒くれ漁師相手に「じょっぱり女」を自称する女将は、おふくろみたいな抱擁力を示す。
寡聞にして内藤綾子という作詞家を知らなかった。しかし、この一編が、単なる思いつきではなく、あれこれ考えあぐね、書いては捨て書いては捨ての、努力の成果だろうことは想像に難くない。酒場のママと客、舞台は雪国というのは、よくある設定。大ていは過去を持つ男が、感慨を女の面影に重ねるか、その逆に女が男にすがり気味というのが相場だ。それを色恋ぬきの、もう一つの物語に仕立て直した着想と、詰めの粘着力には感じ入る。
勝負の"歌い出し2行分"というのは、都々逸に似ているかも知れない。含みのある表現が、きれいに決まると「よッ!いいねぇ」と手を叩きたくなるあの間合いだ。意表を衝いて「ン?」の気分にさせて、おしまいをきれいに落とし込む手口もある。「涙の売り買い」のあざとさギリギリの危ない橋を、うまく渡りおわしたこの人の仕事にも、通じる気がする。
作曲した西つよしの頭2行分のメロディーの納め方にも、似たようなことを思った。南郷達也のイントロは、エレキギターを使った北の海の荒れ方で、歌を発端からあおる。大石まどかの歌は、べたつかずこざっぱりと、女将の気っ風のよさと優しさを説得力のあるものにした。こういう作品がヒットすれば、演歌も少しは景色が変わるだろう。
僕は2月、東京・明治座の「松平健・川中美幸特別公演」に出演している。終演後はお仲間役者との反省会!?のほろ酔いで、鼻唄など歌いながら宿舎へ帰る。
♪口紅が濃すぎたかしら 着物にすればよかったかしら...
は、星野哲郎の『女の港』
♪くもりガラスを手で拭いて あなた明日が見えますか...
は、吉岡治の『さざんかの宿』である。