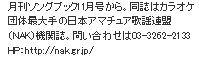大晦日、ドカドカとやって来た客が、ドカドカと帰る。葉山の海の夕陽に乾杯!の趣向が「ゆく年くる年」の途中まで続いたのだから、みな相当に酔っていた。静かになったから、餅を少し焼く。大きめの蒲鉾みたいな奴を薄く切って、面倒だからチンする。なぜか紅色の餅がぷくんとふくれて、しゅわっとしぼんだ。どうして赤いのかは、匂いと味で判明する。どうやら桜エビが搗き込まれているのだ。潮の香の餅ねぇ、土地の味で風流な越年だ...とは思ったが、誰の手土産なのかが思い出せない。ま、いずれ湘南の客の誰かだろう。
ふと思いついて、本間由里の『石狩挽歌』を聴く。「いいのよ、これが...」と僕に耳打ちしたつれ合いは、まだ帰宅していない。歌社会で仂いていて、この夜は懐メロ大会のテレビの楽屋あたりか。終われば軽く一杯!になるのだろう。結局、僕と一緒に本間由里を聴くのは、おなじみの愛猫風(ふう)と、三ヵ月ほど前からの新入りパフ。全身まっ白なのが名前の由来だが、子猫のくせにじゃれ方が超過激。ダッシュ!体当たり!を繰り返して、風を閉口させるパワーは、外人猫の混血かも知れない。
≪なるほど、なかなかの味わいだわ...≫
本間の歌についてだが、まず声味。ほどのいいかすれ方で、手触りが柔らかい。次にフィーリングだが、洋風な生活感に倦怠のスパイスが少々。高音部にやんちゃな覇気が加わるあたりに、好感を持つ。感性が不良熟女なのか?
もともとは、北原ミレイのヒット曲。なかにし礼、浜圭介に呼ばれて聴いた。あれは赤坂の日音の一室。「どうだ!」と浜が眼をギラつかせたから、僕はなかにしに「いいね」と答えた。ミレイはこれで、阿久悠のトラウマから脱出できるだろうと思った。『ざんげの値打ちもない』『棄てるものがあるうちはいい』『何も死ぬことはないだろうに』と、三作続いた阿久作品が、ひどく胸につかえていた。とうとう歌えなくなってしまったほどで、そんな"暗さ"からミレイは『石狩挽歌』で歌手として生還した。
しかし...と思い返す。ミレイが歌った『石狩挽歌』の向こう側、北国の空には暗い雲がたれこめていた。ところが本間のこの歌の向こう側の空には、雲に切れ間がある。心なしか薄陽が差してさえいる。そこの違いがこの歌を、今日的な色あいにしているかも知れない。昨今、右傾化の流れがやたらうさん臭く、世情はなしくずしに暗めだ。そんな中では、"どんより感"が薄めの方が泌みる。聴き終わって「さて!」と、時流へ視線を移す余力が残る。しっかり考えなくちゃな、待てよ、考えているだけで本当にいいのか?
本間由里は30年余のキャリアを持つ。結婚、子育てで一時中断したが、ここまで歌えるのだもの、歌の虫が納まるはずがない。近作CDに『東京暮情/風浪記』があり、作詞は門谷憲二、作・編曲はいずれも川村栄二で、彼が本間のダンナだそうな。
ところで冒頭の紅い餅だが、元日、あちこちへ問い合わせたら、大磯在住の歌手沢チエのお土産と判った。「大阪には、昔からあるらしいのね」の一言で、磯の香、湘南もの...は勝手な思い違いと知る。そのまま書いたら新年早々の誤報第一弾、危い、危い...である。