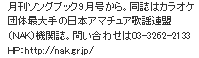手許に一枚のCDがある。『MOSS WAVE 1968~1984』のタイトルで非売品。これは友人寺本幸司を主人公にしたパーティーで配られた。収められているのは19曲。浅川マキの『夜が明けたら』や『かもめ』下田逸郎の『踊り子』南正人の『海と男と女のブルース』桑名正博の『哀愁トゥナイト』や『月のあかり』リリイの『オレンジ村から春へ』沢チエの『夜の百合』などが並ぶ。演歌歌謡曲にフォークやロックと、ヒット戦線が何でもアリだった"あのころ"を偲ばせる歌ばかりだ。
パーティーとは8月6日夜、原宿のライブハウス「クロコダイル」で開かれたテラ(僕は寺本をそう呼ぶ)の80才を祝う会。CDに収められた歌たちは、彼がプロデュースした思い出の作品である。僕は歌謡曲人間だからとても歌えはしないが、それぞれの曲に個人的な思いもからむ。大ヒットこそしなかったが、みんないい作品でテラの音楽観なり時代感覚なりが、その背景にあるのだ。
「僕は月島の生まれでねえ...」
彼はパーティーのステージで、そんなことから話しはじめた。誕生会の世話人たちに「生前葬にはするなよ」と念を押した人間が、何と小1時間も"生い立ちの記"を語り続けて、僕らを驚かせた。面白おかしく...と配慮はされているが、それにしても長い。やむを得ず僕は焼酎の水割りのおかわりを続け、次第にそっちの方に酔った――。
作品集の発端の1960年代後半から、僕は三軒茶屋の"お化け屋敷"と呼ばれる古い西洋館に住んでいた。その一室、卓球がやれるくらい大きな部屋を占拠して、テラは僕んちの同居人第1号。飲みに来るのはテラの側の浅川マキ、下田逸郎らにパントマイムの青年やコピーライターの娘など種々雑多。僕の側は勤め先スポーツニッポン新聞の後輩に、売り出し前の作曲家三木たかしや中村泰士、たまに作詞家阿久悠、石坂まさをとその連れの阿部純子(のちの藤圭子)ら。面白がるレコード会社やプロダクションの有志が加わって、連夜ごちゃまぜの大騒ぎである。70年代に入ると僕がスポニチに若者ページ「キャンバスNOW」を立ち上げ、テラにプロデュースを頼んだから、その書き手も参入した。島田荘司、喰始、石原信一、生江有二、中村冬夫らで、後にそれぞれが名を成している。
テラはそんな安手の梁山泊を仕切っていたかと思うと、ふいと姿を消出す出没ぶりで仕事をこなし、その一部始終を僕は見守った。おデコで物を言うような発言に妙な説得力があり、やがて彼は音楽工房「モス・ファミリー」を興す。パーティーの述懐で面白かったのは①に画才で、子供のころにそのご褒美で、駄菓子屋の"もんじゃ"にありついた。②が瞬発力で、運動会は初速でトップに立つが、いつもそのうち抜かれたそうな。栴檀はふた葉にして...の類いか、長じて彼を腕利きの仕事師にしたのは、独特の美意識と、桟を見ての瞬発力だったろう。
クロコダイルには120人を越すテラの仲間が集まった。みんな本音のつき合いの親しみ易さがいい雰囲気を作る。"ロックテイストの宴"で、参加者はみなそれらしいいでたちだったが、よく見ると多くがそれぞれの年輪を示す風貌ではあった。
≪80才?何がめでたい!≫
そう軽口を叩きながら参加した僕だが、結局はテラの作品集にしみじみ往時を思い返す仕儀になる。考えてみればアルバイトのボーヤから校閲部、整理部と内勤9年の体験は、立派にスポニチの保守本道である。それが取材記者に転じるや、すぐに長髪にパンタロン、ラジカルな記者たちの頭目になれたのは、あのころのテラとその仲間の影響が大だった。ちなみに僕はテラより2才上で、10月に82才になる。あいつも俺も、その時々をめいいっぱい事に当たりながら、成り行き任せで生きて来たということか。双方の既往症は「人間中毒」と「ネオン中毒」だものな。