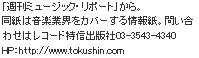地方の友人から、よく電話がかかって来る。
「テレビ、見たよ、元気そうで何より。一度遊びに来ませんか。仲間を集めるから、一杯やろうよ」
北海道や山形、島根だの屋久島だのからのものである。久しぶりの連絡のきっかけは、BSテレビ各局の〝昭和の歌回顧番組〟で、僕はそれに呼ばれてしばしば、
『年寄りの知ったかぶり』
のおしゃべりをしている。主な話題の主は、作家なら船村徹、浜口庫之助、星野哲郎、歌手なら美空ひばり、三橋美智也、春日八郎、村田英雄…が中心。みんな密着取材を許された人々だから、手持ちのエピソードが多い。
「それにしても、よく出ているねえ」
と、友人たちは口を揃える。80才を過ぎて隠居していないのは、彼らの周辺では極めて稀。それなのに君は…と言われれば、
「見た目はともかく、近ごろ体の中身はガタガタでねえ」
と、妙な言い訳をせざるを得ない。出演本数が多く見えるのは、BSのその種の番組、やたらに再放送が多いせいなのだ。
番組制作はテレビ局から制作会社に発注されている。僕が世話になっているのはおおむね3社で、自然、プロデューサーと親しくなる。
「今度はあの人で行こうと思うが、どう?」
「あの歌手についてのネタは、ありますか?」
などの打診がある。しかし当方にも得手不得手はある。僕はもともと密着型の体験派だから、取材し損なっている人が対象だと辞退する。実感のないまま、また聞きや聞きかじりをしゃべる気にはならない。
「だからさ、誰か他の人に頼んでよ」
と言うと、電話の相手は即座に、
「それがねえ、皆さん亡くなってしまって、あのころの話を出来るのは、あんたしかいないのよ」
と来る。消去法による人選か! と、当方は憮然とする。
《しかし、戦後の昭和ってのは。凄い時代だったな》
そんな番組の軒づたいをしながら、僕は考える。戦前、戦中に活躍した作家や歌手たちが、戦後しばらくを支える。NHKの連続ドラマ「エール」で俄然脚光を浴びた作曲家古関裕而など、その代表の一人だろう。そして、先に列挙した僕の親密な取材対象は、いわば戦後の第一期生である。そんな新旧の才能がしのぎをけずって実現したのが昭和の歌謡曲だったろう。背景には、敗戦からの復興、高度経済成長、経済大国への成功、それを象徴する東京オリンピックや万国博、やがてバブルの時代が来て、それが弾ける―そんな激動の時代を、歌謡曲は歌い継いで来た。
紅白歌合戦やレコード大賞が派手な演出で茶の間を興奮させた。あのころ、一家団欒がまだあった。老若男女が同じ歌を一緒に支持し、似た思いを託した。生き方考え方に共通する部分があって、共有された生活感。しかし、その陰には次第に、あてどなさや不安、少しずつふくらむ不満が生まれはしなかったか? 敗戦からの驚異的な復興も、右肩上がりの経済も、庶民の犠牲の上に成り立っていた。やがて人々は、富と貧困を軸にした分断を感じ取る。そんな屈託を慰め、励ましたのも歌謡曲だったろうか?
「平成で終わりかと思ったら、令和になってもまだ昭和の歌ばやりは続くねえ」
「平成の枠組みじゃ、こういう番組は作れませんよ。サザンと安室とピコ太郎じゃねえ」
BS各番組のスタッフと僕は、冗談まじりにそんな話をする。音楽的な好みが世代別に細分化の一途を辿っている。流行歌以外の娯楽も圧倒的に増えた。結果の一つとして、ヒット曲の粒はきわめて小さくなった。
《しかし、ちょっと待てよ…》
と僕は踏みとどまる。戦前、戦中に大きなヒット曲が生まれた背景には、庶民が戦争に動員された苦難があった。太平洋戦争に敗れ、そこから復興する道のりにも、やはり庶民の多くが犠牲を強いられていた。つまり老若男女が好みを一つにしたのは、みんなが苦しさや辛さを共有した時代だったのではないか? だとすればおとなが若者の歌に持つ感想と、若者がおとなの歌に持つ感想とが、
「みんな同じに聞こえて、訳が判らない」
となっている昨今は、何はともあれ極く平和な時代なのではないだろうか?
コロナ禍で仕事も思考も停止状態の昨今、僕はそんな屁理屈を口走りながら、『知ったかぶりおじさん』の繁盛を、とても幸せなことだと思ってちょろちょろしている。