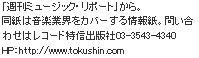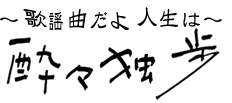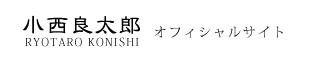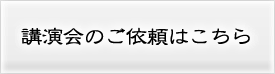右手で右へ襖をあけてズイと入る。豪商小曽根六左衛門の邸の離れ。
「やあお慶さん、よう来たな…」
後ろ手で襖をしめながら、ヒロイン川中美幸に声をかける。明治座3月公演「天空の夢・長崎お慶物語」の一幕四場の僕の仕事はそこが始まり。
「ごぶさたをしまして…」
と、艶然の川中、
「相変わらず別嬢さんたい」
と、長崎弁がまずまずかな?の僕…。
二人っきりの場面10分ほどのけいこが終って、
《ま、こんな調子で…》
と合点しかかった僕に、
「頭領!襖のあけ方が変ですよ」
と、友人の綿引大介が小声で言う。舞台下手からの出だから右側は客席、襖を右へあけてはその収まり場所、つまり戸袋部分がないという指摘だ。
「そうか、襖は左へあけなきゃいけないんだ!」
けいこ場は全部、そこに座敷があるつもり、手前に襖があるつもり…でやっているから、そこまでは気がつかなかった。
《キャリアの浅さがこんなところに出るか!》
肩をすくめてけいこ場の隅、今度は左手で左へ襖をあける仕草をしていたら、
「右手で左へ…の方が、きれいですよ」
と、もう一人の友人・丹羽貞仁から声がかかった。右手で襖を左へあけ、川中に声かけながら、上半身を右にひねって後ろ手の右手でしめる。
「その方が絵になる。日舞ではそうします」
と、丹羽はニッコリした。なるほどな、客席は右側にあるんだから、左手でしめようとすると、上半身のターンが逆になって、確かに客に背を向けることになる…。
《基礎というか素養というのがない。俄か役者のやばいところか…》
息子みたいな年齢の友人たちのアドバイスに、僕は素直に頭を下げるっきゃない。
その目の前で、もっと若い岡田賢太郞が長い棒を振り回して、捕り手の一人げいこをしている。5年前の7月、同じ明治座川中公演の「お喜久恋歌一番纏」が僕の初舞台だったが、その二幕一場に彼も居た。火消しの若者の一人で、人を呼びに走り去るだけの役。もっと長く舞台に居たいだろうに…と気になったものだが、今回はセリフもあるし川中にもからむしで、とても生き生きとしている。同じシーンで兄貴分をやり、岡田に火消しの走り方を教えていた伊吹謙太朗も久しぶりにご一緒。
「馬渕玄三さんのところに居たって言ってたよね」
「ええ、それで三島大輔先生を紹介されて…」
けいこ場でそんな思い出話の続きになる。たまたま出た「家族そろって歌合戦」で歌唱賞を貰い、人にすすめられての歌手修業。
「でも、その前からやってた役者の方が、俺には向いてるのかななんて思ってですね…」
ベテラン俳優が今になっても、昔話にテレたりするところがいい。
それやこれやの人の輪で、芝居の世界もなかなかの居心地。そして相変わらず、目を見はるのが川中の集中力だ。出ずっぱりセリフ山盛りのヒロイン役を、短期間で心身になじませていく。けいこの途中もNHKののど自慢に出たり、ドラマ「てっぱん」に顔を出したりしながらのことだ。
幕末の女貿易商お慶の川中と、番頭役・田村亮の心の通わせ合いが縦糸のドラマ。笑わせたり泣かせたりのヤマ場があちこちにあって、テンポは快適、展開はスピーディー。僕なんか、中身を全部よく知っていても二、三度、目頭が熱くなる。
《演出家って、どんな反応をするもんだろう?》
と、華家三九郎氏(もともとはNHKでドラマを作って著名な大森青児氏)を盗み見たら、これが表情豊か。見せ場の一つ一つにうなずきながら、お客みたいに一喜一憂する気配で「なかなか面白いよ」なんて言っている。その後ろで長崎弁指南の先生が、めがねをはずして目をこすった。
このコラムが読者諸兄姉の眼に触れるころは、この芝居、3月6日初日だから、もう幕があいている。僕の襖のあけ方や、右ターンしてのしめ方も、ま、何とか板についていることだろう。