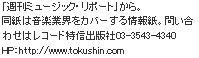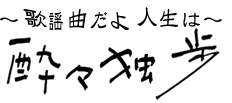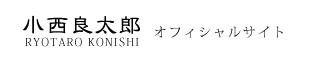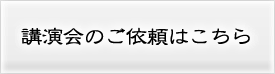帝国ホテルの宴会場が、突然春景色になったから驚いた。祭壇の右手に桜、左手はこぶし、まん中をうねるのは緑の信濃川で、あとは一面に菜の花、チューリップ、スイートピー、フリージア...、背後に紅まで出て、中央にいい笑顔の遠藤実の遺影がある。12月1日夜開かれた彼の七回忌の集い。
「越後の春を作れと言われて、この時期でしょ、花集めが大変でしたよ」
友人の花屋、マル源の鈴木照義社長が小声で言う。彼には三木たかしの葬儀の祭壇で「空前絶後」を注文、星野哲郎の時は「なみだ船」や「兄弟船」の荒れる海を作ってと、無理難題を言った仲だから、有無相通じる笑顔だが、それにしても見事!
なだ万の料理がフルコースで、ほどほどの酔いの参会者250人相手に、遠藤のヒット曲が並ぶのは、七回忌だから賑やかにの主催者の思いがあり「遠藤実 歌と共に」のタイトルにも表れてのこと。
それならば...とばかりに千昌夫が一口噺を幾つか。そのうえで「世界の3大ワルツの」を名指す。「テネシー・ワルツ」「芸者ワルツ」それに彼の「星影のワルツ」だと言って爆笑させるのが自前の曲紹介。さっと切り替えて情感たっぷりめの歌は、さすがの年の功か。五月みどりの「おひまなら来てね」が懐しく、北島三郎は「ギター仁義」ではなく「親父」で、婿どのの北山たけしが手伝う趣向。縁のあった歌手たちもステージに勢揃いしたが、とっさのことで数え切れなかった。
僕は一度だけ、遠藤に作曲を依頼したことがある。スポニチに連載した「阿久悠の実戦的作詞講座」の藤圭子編の当選作。こちらから何の注文もなく、あちらから特段のコメントもなく、さらさらっと「さすらい」が出来上がったが、当の藤は、
「ご詠歌みたいね」
と眉をひそめた。音域が狭く、起伏も地味めのメロディーが、遠藤の歌の特徴と知るには、彼女はまだ若かった。歌手として技の見せどころがないと思ったのだろう。
しかしその感想は、その実、遠藤の世界を言い当てて妙だった。「北国の春」「すきま風」「みちづれ」など、彼の作品の多くが、ロングセラーになった理由がそこにある。シンプルなメロディーラインと奇をてらわぬ穏やかな感興が、庶民の心にじっくりとしみ通る。歌えば歌うほど、聞けば聞くほど、生きてくる歌なのだ。その歌づくりの核にあったのは「祈り」の心、信仰心の合掌ではなかったかと、僕は思った。そんな原稿がこの夜、参加者に配られた本「不滅の遠藤実」(橋本五郎、いではく、長田暁二編、藤原書店刊)に載っている。薬師寺長老安田暎胤師、不破哲三氏に船村徹、元トーラス五十嵐泰弘社長らと弟子の歌手たちが、一問一答形式でそれぞれ得難いエピソードを語っている。その中で一人だけ、屁理屈をこねている拙稿は、少し浮いていたが後の祭りだ。
縁あって僕は船村徹から50年余の知遇を得て、弟子の一人と自認している。その船村と遠藤は強いライバル意識を伝えられて来た。同じ時期、同世代で歌づくりにしのぎを削ったせいだが、ひととなり、作風などはまるで違った。決してそのせいではなかろうが、遠藤と僕の縁は薄めに終わる。全方位外交の流行歌評判屋としては、いささかの悔いが残った。この夜の北島は「うちの師匠」と船村を呼びその歌づくりを「名人芸」とし、それに対して「遠藤先生」の仕事は「職人芸」だと話した。まだ作家の専属制が残り、作家たちの競合が厳しかったころからの体験が、にじむ心地がした。
いではくは、遠藤実歌謡音楽振興財団の理事長職を、師匠の娘遠藤由美子に引き継いだ。あいさつにホッと一息肩の荷をおろした気配が濃い。彼と遠藤のつき合いは、秘書、作詞家として38年、遠藤の生涯のちょうど半分におよぶという献身ぶりだった。いでの紹介で幕切れは「喜びの日の歌」を歌う遠藤の映像になる。「ありがとう」を何度もくり返すその姿に、由美子新理事長は涙を拭った。
冒頭の祭壇〝北国の春〟は6日、新潟市のホテル・イタリア軒で再現された。祥月命日に地元でも偲ぶ会が開かれてのことである。