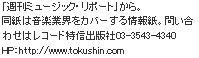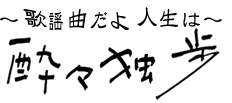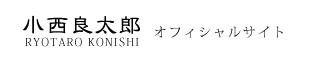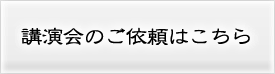《ま、これも〝ゆうすけ〟らしい創作活動の一端か》
そんな感想を先に持ったまま、山田ゆうすけ自作自演のアルバムを聞き始めた。「冬の鳥~高林こうこの世界を歌う」がタイトル。作詞家高林とゆうすけのつき合いは長い。二人は「シルクロード」という同人誌で知り合って、その25周年を記念した企てだと言う。
「冬の鳥」「途中下車」「五条坂」「大阪ララバイ」「神戸メルヘン」「散り椿」「ぶるうす」「センチメンタルジャーニ」「枯葉の中の青い炎」「ラストタンゴ」と、曲目順にタイトルを並べれば、いかにもいかにも...の10曲。高林は関西の人で、友人の作詞家もず唱平に紹介されて僕も旧知の仲だが、寡黙だから詰めて話したことはない。それが―。
歌を書くとなると、秘めた情熱がほとばしるものか、全体的に長めの詞に、彼女なりの思いがあれこれ、多角度に書き込まれている。表題曲はメロ先だそうだが、雪の駅で去って行く恋人の前途を、
〽飛ぶなら高く、飛ぶなら遠く、飛ぶなら強く...
と祈る男心もの。「償いは、美しく見送ること」と思い定めた恋の幕切れだ。
「途中下車」は人生の息抜きの旅のひとときを描く。舞台は田舎町のひなびた宿。漬け物やホッケを肴に、銚子は3本。良い月と良い風を仲間に、男は往時を思い返す。優しい女がいた。悪だけど憎めない奴がいた。父親みたいに忠告してくれた人がいた...。
《どこかで聞いたな、これは...》
ひょいと思い出すのは、銀座のシャンソニエ。ここで歌っていたのは、歌を東北弁でやってのける変わりダネで、確か福浦光洋という人がこの作品を歌っていた。歌手歴30年余の年の功と東北弁が、人生を〝途中下車〟した男のひと夜を、味のあるいい歌にしていたものだ。
アルバムに添えられたゆうすけの手紙には、
「いろんな歌手に提供した作品や、書きおろしも集めてセルフカバーした」
とある。それにしても歌っているゆうすけ本人が、
「歌手としての力量はイマイチ、いやイマニだと思う」
と正直なところがほほえましい。
《ま、歌い続けりゃそのうち〝下手うま〟の境地に辿りつくケースだってあるさ》
とこちらは、冷やかし気分になる。
ゆうすけと会ったのは1998年に、彼が作曲家協会のソングコンテストでグランプリを取った時。選考会の座長だった僕と受賞者の間柄で、もう20年を越すつき合いになる。当時の受賞者で作曲の花岡優平、田尾将実、藤竜之介とゆうすけ、作詞の峰崎林一郎の5人組と「グウの会」を作った。「愚直」のグで、めげずに頑張れ! の意だったが、その後彼らはそれぞれに、歌社会にちゃんと居場所を作っている。
ゆうすけはこのところ、ネット関連のビジネスやSNSを使うプロモーションで、独自の仲間やコミュニティを作る作業に熱中、それらしい手応えを感じているらしい。そんな才覚を買われて、作曲家協会事務局のIT関係の仕事を引き受けてもいる。各メーカーへの売り込みはもう諦めた様子。彼我の作品的乖離が大きいし、相手側の顔ぶれも組織も当初とは大きく変わっていよう。最近、白内障の手術をした66才だが「やりたいことをやる」にはいい年ごろだ。70才で舞台役者になった僕の前例だってあるではないか!
話はアルバムに戻る。ゆうすけのメロディーは、フォーク系の穏やかさにポップスのヤマ場を作って、人柄なり。「大阪ララバイ」にはムード歌謡の匂いがあり「神戸メルヘン」は3連ものと、それなりの工夫をこらす。「五条坂」は老舗の陶芸店を守る女性が、去って行った窯ぐれを待つ切ない心情を歌う。高林の詞の「からだを全部耳にして」男を待つ切迫感と、曲の穏やかさのバランスが、聴く側にどういう味で届くものか? 「窯ぐれ」は「技術を磨くために、全国の窯元を渡り歩く職人」を指し「昨今はそんな職人も数少なくなっている」と、高林の曲目メモにあって、教えられた。
ゆうすけのこういう仕事は、
「トップダウンではなく、ボトムアップで仲間を増やしていく」
のが狙い。今年はもう1枚、友人の作詞家堀越そのえの作品集を作るそうな。手間暇と経費もかかろうが、熟年の初志なら、こちらは双手をあげて賛意を表すことに決めた。