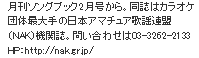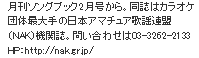「この際だから、演歌の王道を行きましょう」 と、川中美幸とそのスタッフは、肚を決めたらしい。昨年その路線の「海峡雪しぐれ」を出し、今年は「恋情歌」で、姿勢を踏襲している。作詞がたかたかしから麻こよみに代わったが、作曲弦哲也、編曲南郷達也は変わっていない。
僕は去年の2月、明治座で「海峡雪しぐれ」をたっぷり聞いた。彼女はショーで毎回歌ったし、休憩時間にも繰り返し流されていた。共演者の僕は楽屋でそれを聞きながら、彼女らの言う「この際」の意味を考えていた。ここ数年、女性歌手たちの仕事はポップス系に傾倒している。アルバムやコンサートではカバー曲が目立つし、シングルもポップス系の味つけが増えている。
川中はきっとそんな流れを見据えて「演歌の王道」を極め、守る思いを強めるのだろう。ベテランの域に入って、内心「せめて私ぐらいは…」の自負も抱えていようか。
改めて2作品を聞き直す。前作「海峡…」は、
〽いまひとたびの春よ、春…
と、幸せを待つ女心が一途で優しいが、取り巻く気候はきびしい雪しぐれだ。それが今作「恋情歌」だと、
〽たとえ地の果て、逃れても、あきらめ切れない恋ひとつ…
と女心が激しくなり、情念がとても濃いめだ。弦が書いたメロディーも、前作はやや叙情的だったが、今作は冒頭からガツンと来て、起伏も幅が広く激しい。
川中の歌唱は2曲とも前のめり気味。思いのたけ切々で、主人公の女性の胸中を深く歌い込もうとする。演歌本来の「哀訴型」で、これが彼女の「王道」や「本道」の中身だと察しがつく。その実彼女は「ふたり酒」や「二輪草」の、歌い込まないさりげなさや暖かさの包容力でヒットに恵まれた。それはそれで身の果報だろうが、本人はもともと、身をもむくらいに切々と、やっぱり歌を泣きたいのだと合点がいく。
はやりものや文化は何事によらず、古い良いものの極みを求める努力と、古い殻を打ち破る新しいエネルギーが二本立てで、せめぎ合って前へ進むものだろう。そういう意味では、川中が「この際…」と思い込む世界は、古い側に属すことになる。しかし古い器に新しい酒…の例えもある。昔ながらの「哀訴型」に、今を生きる彼女の感性が投影され、極みを目指そうとするなら、それはそれで今日の産物になる。作家もスタッフも、呼吸しているのは現代だ。
僕は新聞屋くずれ。長く媒体特性を軸に見なれない面白いもの、時流の先端になりそうなものに強く反応して来た。下世話な新しいもの好きである。そのせいか、女性歌手たちのポップス傾倒に好意的だが、しかし、それにも得手不得手、似合う似合わないはある。それなのに、一つが当たると一斉になだれを打つこの国の付和雷同ぶりが、歌謡界も例外ではないのはいかがなものか。対極にあるものをないがしろにしない踏み止まり方も応援したいものだ。
話は変わるが、市川由紀乃の新曲「秘桜」を聞いて《ン?》と感じたことがある。彼女もまた「哀訴型」の歌手だが、その感情表現はやや醒め加減で、情緒的湿度はさほど高くない。そのほどの良さが〝今風〟なのだが、感じ入ったのは彼女の歌ではなく、作曲した幸耕平の筆致の変化だ。市川のヒットほかを書き続けて、
「この辺で俺も一発!」
とでも言いたげな「本格派」への試みが聞き取れる気がする。
もともと打楽器に蘊蓄が深い経験のせいか、リズムに関心の強い人と聞いていた。作品そのものも軽快でリズム感の強いものが多い。演歌を書いても多くの歌手に、リズム感の肝要さを説くエピソードをいくつも聞いた。大月みやこでさえそう言われたと話したものだ。
それが今作では、リズム感第一を棚にあげてメロディー本位、もう一つ先か上かの作品へ狙いがすけて見える。作品の色あいは演歌よりはむしろ歌謡曲だが、亡くなった三木たかしの世界を連想した。いずれにしろ演歌、歌謡曲を守ろうとする人や逆にそれを目指す人がともに頼もしい時期である。
僕は役者としては川中一座の人間だが、長く彼女とは会えぬままになっている。時節柄芝居の話がなかなかで、お呼びがないせいだが、彼女の側近の岩佐進悟からは、
「会えぬ日が続き寂しい限り。コロナが落ち着いたら是非とも一献」
なんてFAXは来る。もちろん委細承知! である。

中村美律子の「あんずの夕陽に染まる街」を思い返しながら、葉山・森戸海岸を歩いた。花岡優平の作詞作曲。迷いつつも同窓会で帰郷した女性が、泣きたくなるほど愛しい日々を振り返る。街は夕陽に染まって、それがどうやら淡紅のあんずの花の色。心に灯るのは、あの人が好きだった純情時代のあれこれ…。
ニューバージョンのただし書きがついていた。
「こういう時期に似合いだから…」
と、装いを改めての再登場か。ゆったりめの歌謡曲、どこか懐かしいメロディーに、花岡がよく書く〝愛しい日々への感慨〟が揺れる。確かにこの時期、演歌で力むよりは、こういう〝ほっこり系〟が、妙になじむ。
《あんずなあ、季語とすれば春か…》
昼さがりの海岸を、巣ごもり体重増対策で歩いていて、歌の季節感に行き当たった。というのも、ひょんなことからJASRACの虎ノ門句会の選者を頼まれてのこと。作詞家星野哲郎の没後10年の会で、門弟の二瓶みち子さんにやんわり持ちかけられたいきさつは、以前にこの欄に書いた。最近令和2年分から小西賞に、
「ママの手を離れて三歩日脚伸ぶ」関聖子さん
を選ばせてもらった。会長のいではく賞は、
「音重ね色重ねゆく冬落葉」これも関聖子さん。
弦哲也賞は、
「自然薯の突き鍬錆びて父は亡き」川英雄さん。
いわば歌書きたちの句会年間3賞で、関さんはダブル受賞、大病をされた後とかで、これで元気を取り戻されるかも…と後で聞いた。
森戸海岸は、葉山マリーナから森戸神社まで。逗子海岸や一色海岸と比べるとこぶりだが、正面に富士山が鎮座する。ヨットやウインドーサーフィン、シーカヤックなどに、近ごろ流行りの一寸法師ふうスタンドアップパドルボードに興じる人々が点在してにぎやかだ。海岸には老夫婦の仲むつましさや犬の散歩、走る若者、娘グループの笑い声などがほど良く行き交う。
《しかし、あれはやり過ぎだった。意あまって脱線したようなもんだったな》
中村美律子の笑顔を15年ほど昔にさかのぼる。彼女の歌手20周年記念アルバム「野郎(おとこ)たちの詩(うた)」を作ったが、シングルカットしたのが「夜もすがら踊る石松」で、阿久悠の詞に杉本眞人の曲。和製ラップふう面白さに悪乗りして、中村の衣装をジーンズのつなぎ、大きめのハンチングベレーで踊りながら歌うと意表を衝いた。ところがそれでテレビに出したら、あまりといえばあまりの変貌に、彼女のファンまでが、
「あんた、誰?」
になってしまった。
そのアルバムは阿久の石松をはじめ、吉岡治の吉良の仁吉、ちあき哲也の座頭市など、親交のある作詞家に無理難題の野郎詞を書いてもらった。中村の衣装は勢いあまっての失敗だったが、作品集自体はその年のレコード大賞の企画賞を取っている。もっともその直後に中村が東芝EMI(当時)からキングに移籍。販売期間がきわめて短く、〝幻のアルバム〟になったオマケもついた。
森戸海岸が好きな理由はもう一つ、神社手前の赤い橋そばに、古風でいいたたずまいの掲示板がある。これが葉山俳句会専用で、毎月の句会の優秀作が掲示されている。先日その前に立っていたら妙齢のご婦人に、
「皆さん、お上手ですよねえ」
と同意を求められた。
「そうですね、実にいい!」
と、僕は笑顔を返したのだが、短冊にきれいな筆文字の一月例会分では、
「小魚の跳ねる岬を恵方とす」矢島弥寿子さん
が、海のそばで暮らす人の実感いきいき。またしても書くが〝こんな時期〟だからこそ、小さな生き物のエネルギーに、先行きの望みを託す気持ちに同感する。
もう一句、胸を衝かれたのは、
「かの山もかの川も見ず年明くる」増田しげるさんで、コロナ禍自粛のままの越年なのか、もしかすると…と、まだ見も知らぬ詠み人の体調まで少し気になったのは句の静かさのせい。
神社から海岸通りへ戻り、御用邸方角へ少し歩くと真名瀬(しんなせ)という漁港がある。こちらもこぶりで遊漁船が四、五隻、未明から昼ごろまでに出たり戻ったり。小さな舟の二、三隻は漁師の仕事用か。僕が散歩する時刻には、みんな一仕事終え人影もない。それを見回して、
《ふつつかながら俺も一発いってみるか…》
とその気になって一句ひねった。
「漁港のどか、マストに鴉こざかしげ」
別に鴉にふくむところがあるわけではない。すいっと横切ったカモメを目で追うさまがそう見えただけのことだ。

殻を打ち破れ229回
『王将一代』と『王将残照』という歌を聞いている。正月の4日、コロナ禍の急激な拡大で、いつも自宅に人を集めた忘年会も新年会も今回はなし。つれあいは仕事で東京へ出ており、一人きり、猫二匹相手の自粛生活のひとときで、机の上のCDに手が伸びた。2003年10月22日発売とある。
作詞は友人の峰﨑林二郎、作曲と歌は50年来のつき合いの佐伯一郎だ。2曲とも将棋の坂田三吉が主人公、
♪浪速根性どろんこ将棋 暴れ飛車だぞ勇み駒…
♪苦節春秋十と六 平で指します南禅寺…
などと、勇ましいフレーズが並ぶ。それに哀愁ひと刷毛の曲をつけ、佐伯の歌は声を励まし節を動員して「ど」のつく演歌。めいっぱいに歌い切って“どや顔”まで見える。
≪彼の会もにぎやかだったな。昔なじみの顔が揃って、“地方区の巨匠”の面目躍如だった…≫
暮れの12月23日、浜松で開かれた佐伯のイベントを思い返す。畠山みどり、川中美幸、北原ミレイをはじめ沢山の花が会場を取り巻く。ロビーには芸能生活65年分の記念の品がズラリ。
「小西さんと一緒に出てるよ、ほら!」
と、和枝夫人の明るい声に呼ばれると、大型テレビに彼が歌い、僕が能書きを言っている場面が映っている。あれはスポーツニッポン新聞社を卒業 NHKBS「歌謡最前線」の司会を任された番組の1シーンだから、2003年ごろのものか。開演前のひととき、会場には佐伯の歌声が流れている。得意とした岡晴夫のヒット曲や船村徹作品のあれこれも。
そう言えば昔々「船村徹・佐伯一郎演歌ばかの出逢い」というアルバムのライナーノートを書いた。1960年代の中ごろ、飛ぶ鳥落とす勢いのヒットメーカー船村と無名の若手歌手佐伯が意気投合して、曲を書き歌い合った珍しいコラボ盤。それに書き物で加わった僕も、ご他聞にもれぬ“演歌ばか”で、取材部門に異動したばかり、28才の駆け出し記者だった。
その前後から佐伯との親交が始まる。やがて彼は故郷の浜松に戻り、作曲家・歌手・プロデューサーとして地道な活動に入った。熟年の歌手志願をレッスンし、成果が上がれば芸名と作品を与え、レコード化もして地域のプロ歌手へ道をひらいた。人気が出れば仕事の場も紹介、そのうちに佐伯一門が東海地区で活躍するにぎわいを作る。地元で盛大なディナーショーをやり、勢いに任せて弟子たちを引き連れ、浅草公会堂でコンサートを開くのが恒例になった。トリで歌いまくるのはもちろん佐伯で、僕はいつのころからか彼を“地方区の巨匠”と呼ぶようになった。テレビで顔と名前を売る全国区の人々だけが歌手ではない。地方に根をおろし、ファンと膝づめで歌う歌手たちも、立派なプロだし地方区のスターなのだ。
佐伯の娘に安奈ゆかりという女優が居る。彼女と僕は一昨年と昨年、川中美幸の明治座公演で一緒になった。その共演を一目見ようと、昨年春、佐伯は明治座に現れた。「無理をするな!」と止めたのだが、言い出したらきかぬ彼は車椅子で、それが彼と僕の最後の歓談になった。
タネ明かしをしよう。昨年12月23日のイベントは、実は83才で逝った彼の葬儀だった。コロナ禍で家族葬ばかりのこの時期なのに、演歌一筋に生きた彼のために「ラスト・ステージ」を演出したのは和枝夫人や長男の幸介、安奈ら遺族の一途な思いで、会場はイズモホール浜松の貴賓館。乞われて祭壇の前に立った僕は
「おい、ここはまるで浅草公会堂みたいだな」
と、少ばかり思い出話をした。冒頭のCDは、その日会葬御礼として配られたものだった。