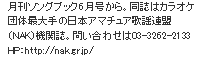殻を打ち破れ232回
≪「ドキュメンタリー青春」なぁ、当時田原総一朗が仕切ってたシリーズで、テレビ東京の人気番組だった。戦闘的な語り口が若者に受けていた…≫
友人の寺本幸司が上梓した「音楽プロデューサーとは何か~浅川マキ、桑名正博、りりィ、南正人に弔鐘は鳴る」(毎日新聞出版刊)を読んで、50年近く前の日々を思い出した。寺本が出演したのはこのシリーズの一本「新人狩り」で、彼が浅川マキを世に出すために奔走する姿を追った。一部分を三軒茶屋のわが家で撮影したのは、寺本が初代の有料同居人だったせいで、家主の僕にも出ろと言う。
「居候のテラが主役で俺が脇役? そんなもんに出られるか!」
と冗談めかして断った。僕らの同居は業界内極秘で、代わりに小西家を代表チョイ役を務めたのは愛猫のキキ。眼が金色と銀色の奇っ怪なかわいさから、その名があった。
寺本の本はサブタイトルにある4人のシンガーソングライターとの出会いから別れまでが中心。とりわけ彼がこの世界に入って一からを共にした浅川のことに、相当な紙数が削かれている。寺山修司と組んだ歌づくりや、新宿の映画館の地下にあった小劇場「蠍座」でのイベント「浅川マキを聴く会」の成功などのあれこれには、僕も首を突っ込んでいた。当時の僕はスポーツニッポン新聞の音楽担当記者から文化部長になる30代後半。面白いものには片っぱしから反応して、紙面に新風を!と気負い込んでいた。その眼の前で寺本が奮戦、黒づくめのマキが“アングラの女王”として若者たちの耳目を集めていくのだから、当然こちらもワイワイ・ドキドキになる。
ちょうど1960年代後半から70年代、学園闘争から安保闘争、ベ平連、成田三里塚闘争など、若い世代が闘争的だった時代である。僕は大学闘争で頑張った青年たちを書き手に、スポニチに特集「キャンバスNOW」を作った。若者たちによる若者たちのページで、寺本にはそちらのプロデュースも頼んだ。そのせいか、おんぼろ西洋館の2階大小5室のわが家は、若者たちのたまり場になる。寺本がフォークからロックへ手を広げていて、僕の方は演歌、歌謡曲系。それに放送作家、ルポライターとごちゃまぜの酒宴がひっきりなしだ。
売り出し前の作曲家三木たかしや中村泰士、作詞家の石坂まさをが居り、浅川マキのあとにはやがて藤圭子になる阿部純子が来たりする。寺本の仕事の拠点J&K企画室には喜多條忠がいて、マキのための詞を書いていたし、キャンバスNOWのメンバーには石原信一が居たから、近ごろの作詩家協会会長の二代続きが酒を飲んでいた勘定になる。
寺本の本には僕についての記述もある。『今は幸せかい』でカムバックをはかる佐川満男に“元スター”の態度を返上させるために、
「すすめられた椅子にドッシリ座るな、椅子の前の方三分の一に座れば背筋が伸びる」
と忠告したあたりだ。この行儀作法は『君こそわが命』で第一線復帰を目指した水原弘に指示したのが最初。僕は水原、佐川双方の作戦参謀だったが、それも水原の仕掛け人名和治良プロデューサーとの縁や、小沢音楽事務所小沢惇社長の独立と菅原洋一売り出しを陰で手伝ったのが縁になっていた。
寺本の会社は小沢事務所系だった。寺本と僕は同居を徹底的に内緒にした。「小西の家賃は小沢の負担らしい」などの根も葉もない噂を封じるためである。髙樹町の店“どらねこ”で一緒に飲んでも、僕らは別のタクシーで別方向から帰宅した。昨今もそうだがこの業界は、噂がそのまま事実になって払拭出来ないことが多過ぎるのだ。