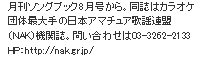殻を打ち破れ234回
ステージに上がる踏み台が3、4歩分。
≪ここでふらついたら、ヤバイよな…≫
と、腹筋に力をこめた。背後の客席には知った顔がそこそこ。年は年にしても彼らには「やっぱり年だな」と思われたくない。
ステージ正面にギタリスト安田裕美の遺影。形通りに献花する。不謹慎な雑念がよぎったのは、故人とは面識がなかったせい。いたわる思いが深い相手は歌手山崎ハコ。安田は彼女の夫君だった。7月4日午後、原宿クエストホール、この日熱海で土石流の惨事を引き起こした雨は、東京にも降っていた。
「最初で最後の安田裕美の会です」
いわば施主のハコが、きっぱりと言い切った。“送る会”でも“しのぶ会”でもない。いつも「裏方に徹したい」と言い「歌い手の後ろで、この人うまいなぁと思いながらギターを弾いていたい」とした安田を、没後1年後に一度だけ、ステージの主人公に据える。そのうえでハコは、みんなと彼について語り、彼が手がけた曲を歌いたかったのだろう。午後の回は音楽関係者やごく親しい人々が客、夜は熱心な安田、ハコファンを中心に一般の人が集まった。
安田は小室等や石川鷹彦のお付きを振り出しにギターを学び、井上陽水、小椋佳、大滝詠一らのレコーディングやツアーの常連になる。スタジオミュージシャンとしての仕事は歌手のジャンルを越え、多岐にわたった。年に一度は渡米、海外のミュージシャンと交流、ギター演奏の奥をきわめた腕利きだ。
そんな安田をハコは終始「安田さん」と呼んだ。慣れない東京で、一途に多難な道を歩き続けたハコからすれば、幅広い人脈と活動の場を持つ安田は、尊敬する先輩で、よき理解者で、やがて同志にもなったろう。大ヒットした『織江の唄』をはじめ、数多くの作品を共にした二人は、九州の娘と北海道の男の縁(えにし)を育て、2001年元旦に結婚、2020年7月6日、死別する。
この日ハコが歌ったのは、阿久悠の遺作の1曲『横浜から』に『SNOW』『BEETLE』『縁』『ごめん…』の5曲。安田が参加したカラオケとハコのギターの弾き語りが合流した。
ハコが詞、曲を苦心して1曲作りあげると、安田は「よく出来たねぇ」とねぎらったらしい。ハコのギターのイントロを「あれ、そのまま使おうよ。とてもいい…」と、安田が編曲に採用したこともある。ハコが興奮し、安田がうんざりしたのは雪。ハコの昔話は、ふるさとの空や雲、神社の石段、ちょうちょやかぶと虫やおばあちゃん…。
それらを安田は、いとおしげに見守った。ステージに山ほど写し出された安田写真は、長めの髪、サングラスの奥の優しげなまなざし、ふっくらした頬、似合いのあごひげ、丸っこい体つき…。その穏やかな包容力が、ハコの問わず語りを見ていた。
≪そうだよな。いつも捨て置けない人なんだよ彼女は…≫
いじらしさやけなげさが、彼女のキャラ。歌は哀訴型で、ひたひたと聴き手に迫る。幼さも含めた純粋さが一途で、それは僕らが世俗にまみれ、いつの間にか磨滅してしまった大切なものだろう。だから僕はハコがデビューしてすぐから40年くらい、断続的に彼女を追跡してきた。
♪伝えたいのはいつだって 抱きしめて言いたい 愛しているよ死ぬほど好きさ 死んでも好きさ ごめん…
アルバム『山崎ハコセレクション~ギタリスト安田裕美の軌跡』のラストソングである。ギリギリまでギターを弾きながら、安田ががんと戦った3年間と、それに寄り添ったハコの思いに、胸が痛い一日になった。