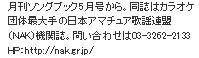殻を打ち破れ255回
坂本龍一が亡くなった。71歳とまだ早過ぎる年齢と闘病の厳しさが、訃報に接した人々の胸を詰まらせた。理知的で「教授」をニックネームとした彼の音楽的業績は、世界中のファンに愛され、尊敬された。YMOの成功、「ラストエンペラー」の米アカデミー賞作曲賞受賞、「戦場のメリークリスマス」の成功などは、誰でもすぐに思い出せる戦果だろう。
一方の闘病は2014年に中咽頭がんを発症、一度は寛解したもの、2020年直腸がんが両肺に移転、ステージ4を公表、その後転移先を追って、一年に六回もの手術に耐えている。
僕は坂本の死を伝えた4月3日付のスポーツニッポン新聞の一面を凝視した。メインの見出しは「坂本龍一さん死去」とストレートだが、それより目立つ大きさの2行が、中央部分に「つらい。逝かせてくれ」とある。本人がピアノに向かう後ろ姿が、全体にボケけた黒一面の中の2行が、かえって浮き上がって、僕の眼を射る。死の一、二日前の言葉と聞く。
≪あれほどの人物が、そこまでの苦痛に追い込まれていたのか!≫
一般論だが、心身の苦痛は、耐えたり秘めるほどその度合いを増す。坂本の場合は世界的なスターである。人前で泣き言などもらさぬプライドも自負もあったろう。「秘す」「耐える」を前提にした闘病九年である。それを続けても一向に“完パケ”にならぬまま、次から次…だった。昔、作詞家の阿久悠ががんに倒れた時、アポナシの僕がたまたま医師の説明に立ち会う事があった。手術は成功したが転移の有無は「これから徹底的に」との見解である。医師の退室後に阿久がボソッと言ったのが「なかなか完パケにならない」だった。克己心強固で有名な人でも、音楽用語でいらだちを吐き出すのか、不謹慎だが僕はその時はニヤリとしたものだ。
それやこれやを思い返している時、妙な息苦しさを覚えた。“加齢による”ただし書きがつくが、体のあちこちに不具合が出ている身である。パルスオキシメーターで計ったら「92」と出た。
≪いかんな、これは。確か95以下は危険ってことだった…≫
コロナ禍大騒ぎのころ聞きかじった豆知識である。高齢者で既往症持ちはなおヤバイ。家人に近隣の葉山ハートセンターに相談してもらったら「すぐ来い!」の返事。「リアクション過剰だな。ヒマなのかしらん?」
と、また不謹慎に笑って出かけたら、即入院の運びになってしまった。
点滴と投薬で、ひどい“むくみ”を除去することと、節々の痛みに対応する措置を受けながら、自宅と同じ葉山の海を眺める日々である。
入院した翌日、僕は担当の看護師さんの発言に飛び上がった。「このベッドには昔、有名な人が寝たのよ」「ふ~ん誰だろ?」「船村徹という人よ、知ってるかなぁ」春の陽だまりの中の問答とも思えぬ衝撃だった。七年前の平成五月に確かに彼は、この葉山ハートセンターで七時間にわたる心臓手術を受けて一命をとり止めた。駆けつけた僕は、あわや心不全の危機を脱した彼の一部始終を目撃している。病状の違いがあるとはいえ人生の師匠と僕が、かつぎ込まれた集中治療室の同じベッドに身を委ねるとは! そんな偶然があってもいいものか、許されることなのか?
そう言えば60年代のあのころ、坂本の映画二本を撮った大島渚監督は新宿ゴールデン街の電柱にもたれかかっており、唐十郎はドブ板にすわり込んでいた。作詞家吉岡治とねんごろになったのは、作曲家むつひろしとの親交が端緒か。「八月の濡れた砂」の同名の主題歌だったが、監督は藤田敏八で、やはり新宿でトグロを巻いていた。浅川マキが歌い始めたのも新宿。あのころの新宿は異端の若者たちの情熱が毎晩爆発し、僕らはそれにそそのかされていた。
大島渚の「愛のコリーダ」が写真集になり三一書房が摘発された時、僕も警視庁に呼ばれた。露骨さ同じ写真が映倫を通さないままスポニチに載っていた。入手経路を聞かれたが「取材努力」とだけ答えた。驚いたのは隣りの席で尋問を受けていた若い女性が「そのあと、金は取ったんだろ、金は、ン?」と年輩の刑事から怒鳴られた一幕だけだった。