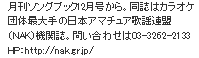殻を打ち破れ 第108回
そのころ僕は、三軒茶屋に住んでいた。国道246を走っていた玉川電車がなくなり、高速道路が出来て10年ほど。つまり東京オリンピックの1964年からしばらくの間だ。古い西洋館の2階5部屋を占拠して、いろんな若者たちが出入りしていた。スポーツニッポン新聞の僕の仲間をはじめ、放送作家やルポライター、コピーライターにカメラマン、デザイナー、メイクアーチスト、パントマイムの芸人から近くの寺の坊さんなど。売り出し前の作曲家三木たかしや中村泰士に、作詞家志望も何人かいた。
そんな中へ時おり、浅川マキが現われた。夜な夜な安酒に酔い、口角泡を飛ばす男たちを見回しながら、マキはコーラ一点ばり。ボソボソッと口をはさむ中身が、なかなかに重め、深めで、キャッチフレーズの“アングラの女王”そのままだった。彼女のプロデューサー寺本幸司が、僕の家の同居人第1号で、一番大きな洋間に居る。だから僕は、マキがキャバレー回りの歌手から、伝説のブルースシンガーに変貌する一部終始を見聞きした。居ながらにしての密着取材だ。
浅川マキの世界を当初、演出したのは寺山修司である。劇団天井桟敷を主宰した彼が、歌の社会でもひとつ、彼らしい世界を作ろうとした。『かもめ』『ふしあわせという名の猫』『ロング・グッバイ』など多くを作詞、ニューハードのギタリスト山木幸三郎が作曲をした。『夜があけたら』『淋しさには名前がない』などはマキの自作自演。彼女はシンガーソングライターのはしりでもあった。新宿蠍座でのファーストライブが開かれたのは1968年12月13、14、15日の3日間の深夜。
学園闘争から70年安保闘争へ拡大したエネルギーは、70年を境に失速、若者たちは鬱屈の時代に入る。そんな時流を背景にマキは、いきり立つ若者たちに囲まれていた。相前後して僕の家に、作詞家石坂まさおが若い娘を連れて現われる。「この子をスターに!」と、舌なめずりして力説する石坂。酒盛りをしていた僕らの無遠慮な視線を浴びて、娘はひどく居心地が悪そうだった。細い肩、薄い胸が「演歌の星を背負った宿命の少女」という惹句ぴったりで、その阿部純子が日ならずして藤圭子になった。出発点はこれも新宿…。
「彼女の歌は怨歌だ」と、作家五木寛之が喝破した。♪十五、十六、十七と、私の人生暗かった…という『圭子の夢は夜ひらく』を支持する、若者たちの心情を読み解いてのこと。藤はあっという間に“時代”の子になった。60年安保闘争のあと、西田佐知子の『アカシヤの雨が止む時』が取り沙汰されたのと似たケースだ。結局藤圭子と浅川マキは、音楽性こそ和洋二色に分れ、精神性も異にするが、“70年のシンボル”としては表裏一体の位置を占めた。
≪何ということだ…≫
あれから幾つかの時代が過ぎて、僕は改めてマキと藤との出会いを振り返る。たまたまの全くの偶然が、後々こんなふうに意味を持ってつながることもあるのだ。マキは今年1月、公演先の名古屋で逝った。藤は歌わぬままスキャンダルにまみれている。僕は複雑な思いで出来たてのマキの追悼盤『MAKI Long Good-bye』を聴いている。