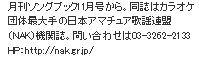殻を打ち破れ136回
≪やっぱりこの人には、六本木界わいが似合いなのかも知れない≫
7月6日の昼、西麻布、長谷寺の阿久悠の墓前で、ふっとそんなことを思った。長い作詞家生活のほとんどを、彼は六本木の事務所や仕事部屋で過ごした。そのせいだろう、彼と僕の食事や酒、それではずみをつけての打ち合わせは、六本木が多かった。彼の行きつけの店、僕のなじみの店。今、思い浮かべるのは大通りの雑踏、角を曲がれば突然、ひっそりと静かな路地…。
1970年、北原ミレイが歌った『ざんげの値打ちもない』の斬新さに仰天して、賛辞を書きまくった僕は、以後37年もの彼との親交を得た。その間の彼の住まいは横浜と伊豆である。睡眠時間も削るヒットメーカーの日々に「なぜ、そんな遠距離から?」といぶかりながら、午前さまになるまで引き止めた夜も多い。近ごろ僕は湘南・葉山に住み、同じ質問を受けるようになった。長い道中の往き来の中で、スイッチがパチンと鳴る。「暮らし」と「仕事」の気持ちが、はっきり入れ替わるのだ。もしかすると彼も、似たような感触を持っていたのかも知れない。
阿久の父は横浜、母は伊豆で葬った。彼はその墓を伊豆に作った。相模湾を一眺する高台のてっぺんで、結局彼もそこに入る。それが今年、七回忌を機に長谷寺に移された。雄子夫人も長男太郎氏夫妻も東京暮らしである。僕ら親しかった人々の墓参の足も、遠のきがちになっていた。
「それじゃ、寂しがりやの彼も心許なかろう」
というのが、皆の気持ちになっていた。だから7月6日は、彼の新住所!?で、七回忌の法要が営まれた。長谷寺は「ちょうこくじ」と読む。福井の永平寺の別院で、徳川家康の時代に開かれたという。由緒正しさで満たされたその境内に、伊豆から移した阿久の墓がある。とび色の石に「悠久」の二文字が大きく刻まれて威風堂々。傍らに
「君の唇に色あせぬ言葉を」
と、阿久が遺した言葉を刻んだ碑を、雄子夫人が建てている。
「しかし、暑い…」
言っても仕方のない言葉を、多くの参会者が口にした。“千年猛暑”とやらの昼さがり、この日関東地方の梅雨が明けた。命日が8月1日だから、彼の法事は日照りの中に決まっている。僕はそれに、彼のライフワークになった「甲子園の詩」を重ね合わせる。毎夏高校野球大会の全試合を熟視して一日一詩、スポーツニッポンに連載したのは何と28年間、363編におよんだ。彼にも僕にも長いこと、高校野球抜きの夏はなかった。
「う~む」
法堂の読経には、都倉俊一、森田公一、飯田久彦、周防郁雄、市村義文の各氏ら、ゆかりの人々が唸った。金糸銀糸の袈裟の僧が、墨染めの僧衣を従えて総勢実に21名。一人こげ茶の衣の僧が経を先導、他に鐘と木魚の担当が各1だが、鐘を叩く棒は野球のバット大である。
「どうだ!っていう阿久さんの顔が見えるようです」
関係者の一人が言って笑った。そう言えば阿久の仕事は全部「どうだ!」とばかりのインパクトの強さに始まり、これ以上なしの完成度を加えて見事だった。